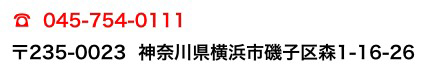今回は、自分の家ではなく有料老人ホームでの看取りをお話しをしましょう。
患者さんは94歳の女性です。だいぶ以前に軽い脳梗塞の既往があり、その後私の外来に毎回娘さんと仲良く一緒に通院なさっていました。
背中はひどく前に曲がっていて立っても私の半分くらいしか背丈がないのでは?というくらい小柄で痩せていましたが、当時87歳にもかかわらず、受け答えはしっかりとしていて、カラオケが大好きで、近所のお友達と出掛けては6時間くらい唄って帰ってくるのだと娘さんがあきれるほどでした。

そんな感じで外来では、いつもニコニコして私の話に本当におかしそうに笑ってくれていましたので、私も外来でお会いして、お話しするのが楽しみでした。
そして昨年、7年目に入るとさすがに94歳になったためか、途端に食欲がおちて、認知症の症状が進んできました。
さらに6月になると発熱と呼吸状態の悪化でついに当院に入院となってしまいました。
本来であれば娘さんの想いはお家で看取りたいとのことでしたが、その娘さん自身が癌を患い治療に専念せざるを得なくなったため、残念ながら本人の病状が安定してもお家には帰れない事が判明しました。。
そこでご家族とお話しをして、94歳であり認知症も進んでおり、今後、食事を摂る量は増えないであろうこと、また徐々に減っていくだろうが、点滴や管からの栄養投与は本人にとって有益な寿命を延ばすものでも、嬉しいものでもないため、本人が食べたい物を食べれる分だけ摂れればいいのではないか、そしてこのまま自然な経過をみていくことを条件に有料グループホームに入居することとなりました。

その後、グループホームに入ってからも、しばらくはあの可愛らしい笑顔でスタッフを和ませていましたし、私が訪問診療で訪れると嬉しそうに「この先生のファンなのよ」とスタッフに言っていてくれたようでした。
しかし、さすがに寄る年波には勝てず、ほとんど何も口にしなくなり、95歳を迎える前にご家族とグループホームのスタッフに見守られながら、とても穏やかな表情で、少しも苦痛表情を浮かべる事もなく、静かに息を引き取りました。
人生の最期が自宅ではなかったとしても、本来、人としての穏やかで静かな幕引きを、
家族と理解ある施設のスタッフに見守られて迎えることも幸せだったろうと思いました。
関東病院 病院長 訪問診療医 梅川 淳一