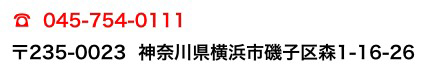さて、最近の訪問診療の患者さんのお話し。
もともとアルツハイマー型認知症で、ご主人と二人暮らしだった女性の患者さん。
その後、食道癌が見つかり放射線療法と化学療法を行うも効果はなく、後は経過を見ていく方針だけの方針になったとの事で、最終的には在宅診療も睨んで当院の外来に紹介されてきました。
初めての外来には、ご主人と娘さんに連れられていらっしゃいました。慣れぬ外来に落ち着きなく周りをキョロキョロされ、私の質問にも単語だけで答えるような感じ。でもこの時点では痩せてはいましたが、まだ歩行もしっかりしていました。
ご主人からのお話では、今までは、一人で外出して迷子になり、ご主人が懸命に探し回り、バスで遠く離れた上大岡で発見したエピソードや、徐々に引きこもりがちになりお家でテレビばかり見ている事。最近は今まで好きだったものも「いらない!」と食べなくなり、温泉卵やコーヒー牛乳、プリンなど限られたもののみ口にする状態であると。
確かに、本人に色々と質問しても「調子悪い」「平気」「うん」「わかった」と簡単な言葉のみが返ってくる状態で認知症としてもかなり末期の状態でありました。
食道癌の進行に伴う食事の通過障害や痛みを懸念しましたが、食事の時の様子をお聞きしても、特にその兆候はない様子でした。とすると、食事の好き嫌いや摂取量が減っているのは、癌ではなく認知症の進行からくるものだろうと判断しました。
その後、2週に1度の外来通院を続けていたのですが、ある日、やはりもうお家から連れ出し当院の外来まで連れてくるのがもう無理であると、ご主人がおっしゃり、娘さんも同感とのことでしたので、さっそく数日後に、訪問診療に伺いました。
ご自宅は、僕が子供の頃に住んでいたようなどこか懐かしく温かい感じの昭和の雰囲気のエレベーターの無いアパートの3階で、一番大きな居間にご主人のものと二つ並べて置かれたベッドに、居心地良さそうに横たわっていらっしゃいました。声をかけるといつもの外来のように「うん、平気」「あまり良くない」など短い言葉をお話ししてくれました。外来でのソワソワした緊張感はそこにはなく、落ち着いた表情で、診療中すぐにテレビを見始めてしまいました。その頃には、水分は薬とともにある程度摂っていたようですが、食事らしいものはプリンと温泉卵くらいのものだったようです。
この頃はご主人が、朝と晩に抱えてトイレに連れていき排泄を促していたようですが、次第にそれも重労働となっていったようです。訪問看護や娘さんはご主人の負担を心配して僕に入院の相談をしてこられましたが、認知症であるゆえ、入院となればせん妄状態になる可能性高く、そうなれば抑制か鎮静をかけねばならず、お話ししなくなったり、本人にとっては不本意で可哀そうなものとなってしまうこと。ご自宅だからこれほど穏やかで安らかな表情で過ごしているのであろうこと。そして幸いに食道癌の末期症状は無く苦痛や、不安、恐怖が見受けられないこと。これらを、ご主人にお話しして皆で支えるので本人の居たい場所、居心地のいい場所としてのご自宅で最期まで過ごさせてあげる方針でいくことにしました。
その決定をしてからは毎週訪問をさせていただき、徐々に黄疸の顔色になっていくのをご主人や娘さんとともに見守っていきました。亡くなる二日前まで変わりなく「うん、大丈夫」「痛くない」とお話ししていて、朝ご主人から息をしていないようだとの連絡を受けて訪ねると、やや横向きに寝たままの姿で永眠なさっていました。この二日はいつもご主人の方に右手を伸ばしてきてそのまま寝ていたとの事。やはり最後も右手は隣のベッドのご主人が寝ていた場所に右手が置かれていました。
最期までご自宅で、ご主人の隣で、癌の苦痛もなく亡くなられて、とても穏やかなお顔でありました。最後にご主人に今までよく看病なさったこと、そしてご本人はとても幸せであったろう事、を娘さんと一緒にお話しし、肩を抱き合って泣いた後お宅を辞しました。
認知症は家族にとっては、厄介で困った病気ではありますが、今回、“自分が癌である事、死にゆく事を忘れてしまうほどの認知症”は、むしろ癌末期においてはありがたいのものなのかもしれないと感じた経験でした。
関東病院 病院長 訪問診療医 梅川 淳一