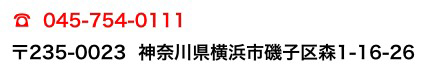さて、訪問診療を始めて最初の頃の患者さんのお話し。
”近くの大学病院に入院中の癌末期の患者さんが「これ以上ここに入院していると殺される?」との事で、急遽在宅へ戻ることになったので宜しくお願い致します。”との訪問看護ステーションからの依頼があった。
「退院日は?」と問うと、「明日だ」という。本来なら本人と、不可能なら家族の方と面談をして在宅での限界や、最期までお家で暮らしたいか、ぎりぎりの状態になったら入院したいか等を確認してからの訪問になるのだが、何しろ急なことなので、翌日退院して間もないお宅に訪問させてもらった。そして診療情報提供書(いわゆる紹介状)を読み、病状を確認後に、ベッドで横たわる患者さんとその周りを囲むご家族にお話し。
身体中が浮腫んでおり、これは前医で1日3本もされていた点滴のためと思う事、この悪性腫瘍が幅を利かせている状態では点滴の栄養は癌に取られ、残りは水だけとなって浮腫みに変わる事、食べたい物、食べられるものをできるだけ最期までお口から食べる事が大切である事をゆっくりとお話しさせてもらった。本人はマグロが食べたいとおっしゃったので、ご家族にお願いして夕食に買ってきてもらうことにし、今後点滴はもうしないことも本人も含めた全員共通の約束とした。それに加え、呼吸が苦しくなる時があるため、在宅で使える酸素も業者にお願いして導入した。
以後、週に2回の訪問診療を続けると、あれだけ手足や顔が浮腫んでいたのがウソのように引いてきて、皺はあるが、ちゃんと筋肉や骨格がわかるようになり、「ああ、昔のお父さんの顔にもどった」とご家族も喜ばれ、身体が軽くなったせいか、ベッドの上で寝返りも打てるようになり、傍に寄ってくる愛犬の頭も撫でられるようになった本人にも笑顔がもどった。
最初の晩にはマグロの刺身を少量だが味しそうに食べられたようだが、それ以後はゼリーやプリン、吸って飲めるウ◯ダーinゼリー、缶詰の果物しか喉を通らなくなっていった。それでも本人に飢餓感や口渇感による苦しさはなく、ご家族に囲まれ穏やかに過ごされた。
退院後2週間目の朝、私の携帯に連絡が入り、急ぎ往診に伺うと、穏やかな顔でいつものベッドに横たわる患者さんが居た。ご家族に聞くと前の晩も苦しそうな感じもなく、朝様子をみると呼吸をしていないことに気付いたそうで、とても静かな最期であったようだ。
人間は”神の与えたプログラム”が組み込まれていて、死への段階を歩み始めると、飢餓感や口渇感は感じなくなるよう、苦しまないようになっている。それをあえて遮るような通常とは違うルートでの栄養投与(点滴や、胃ろうや鼻の管からの流動食)は、かえって本人にとって苦しいだけで、穏やかな最期の先延ばしにつながるのではないかと思う。
関東病院 病院長 訪問診療医 梅川 淳一